 |
高知を代表する名所で、平成10年3月にリニュ−アルして3種類の橋が誕生しました。メインは、かんざしをモチ−フにした欄干がかわいい石造橋。次に、全国から募集したアイデアをもとにつくられた朱塗りの欄干太鼓橋。そして、当時の親柱をそのまま使用した明 治から大正時代のものの復元橋。橋下は水の流れる川となり、両岸は親水公園となり、観 光客にも市民にも好評を得ています。 |
 |
五台山展望台から眺められているのが市街地と目の前の河川で、は国分川・鏡川(※共に二級河川)だと思われます。遠方に囲まれた山並は四国山地、裏側には広大な太平洋が眼下に見渡せられます。 |
 |
古来より吉野川とともに徳島を見守り続ける眉山は“眉の如雲居に見ゆる阿波の山……”と万葉集に詠まれたことにその名が由来するといわれる優美なシルエットの秀峰。絶景が楽しめるビュ−ポイントとして知られ、標高 277mの山頂には展望台のほか、徳島をこよなく愛した明治・大正時代のポルトガルの外交官で文筆家モラエスの遺品や作品などを紹介するモラエス記念館などがあります。 |
 |
梅林橋は南庭の北湖と西湖を結ぶ流路に架かっている色あざやかな朱塗りの橋。別名“赤橋”とも呼ばれ、北湖の西岸付近の庭景、そして松と芝生の緑一色の湖景にアクセントをつけています。すぐ近くには南の梅林が静かなたたずまいをみせており、そのなかで最も 梅林橋寄りにある梅の木は冬至梅と呼ばれる種類。公園内でいちばん早く1月中下旬ごろには可憐でかわいい花を結びます。 |
 |
高知県の中央部、仁淀川支流の柳瀬川流域に広がる佐川町は、「歴史と文教のまち」といわれ、世界的な植物学者牧野富太郎博士や幕末勤王志士の田中光顕翁などを輩出した町で、高知県内で最も伝統のある桜どころです。春には沿線で、紅・白・淡青色などの小花をつけた「芝桜」が出迎えてくれます。 |
 |
瀬戸大橋を渡り四国の愛媛県へ目指して走行する特急列車「しおかぜ」の他、特急列車「いしづち」も含めての走行され4往復にて運営されている様です。詳しくは、JR四国にてご確認下さい。 |
 |
コトデン(高松琴平電気鉄道)築港駅(始発終着駅)からは5分程度、JR高松駅からだと約3分の徒歩で来館が可能な高松シンボルタワ−は、イベントホ−ル・会議室・商業施設及びオフィス機能も持つ多目的な複合商業施設でもあり、また、瀬戸大橋が完成される前までは、四国の玄関として栄えてもいましたが、主に鉄道での利用となる現在では、本州から四国へ訪れる場合、宇多津駅が主流の玄関になっているようにも思えます。 |
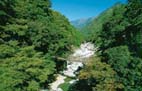 |
シロクチカズラで編まれたかずら橋は、祖谷渓の上流に架かり、長さ45m、幅2m、水面からの高さ14mのところに両岸の大木につながれています。国の重要民俗文化財で、3年ごとに架けかえられます。対岸のびわの滝も見逃せません。 |
 |
オシャレで洗練された芸術文化の新発信基地。土佐の伝統をつたえる土佐漆喰・瓦・和紙などをふんだんに使用した和風建築。約100点の名作を常時展示しており、とっておきは今世紀を代表する巨匠・シャガ−ルの名画コレクション。現代美術・シャガ−ル・郷土関係を3本柱に、美術書閲覧できるア−トライブラリ−、世界の名画が楽しめるハイビジョンシアタ−なども完備しています。 |
 |
徳島市から南へ約5km。緑豊かな丘陵地に建つ文化の森総合公園には、多くの人々に親しまれている図書館、博物館、近代美術館、文書館、21世紀館など文化施設が集中しています。それらを包み込むように施設と関連したテ−マを持つ公園、そして森林が広がっています。 |

